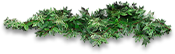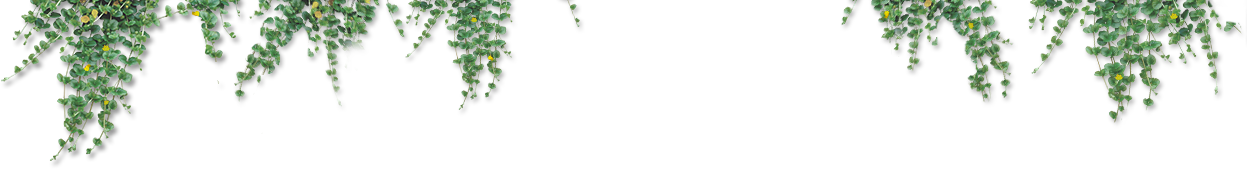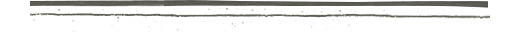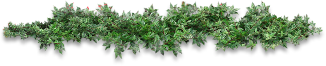
豆知識と活動日誌
2018-06-14 21:53:00
【犬猫のお薬の飲ませ方】
お薬を飲んでもらう必要のある子のお世話に入らせていただくこともよくあります。
わんこの場合は、普通に食欲があり、薬が錠剤ならば、フードにトッピングするとフードと一緒に食べてくれることが多いのですが、難しいのは猫さんです。
猫は一度口に入れても、苦味を感じると薬だけ吐き出してしまいます。
普通にトッピングしただけでは、見事に薬だけお皿に残します。
王道で、口をあけさせて、味を感じやすい舌の先のほうを避けてのどの奥に放り込めればよいのですが、一番信頼関係の強い飼い主様でも慣れないと難しいことなので、シッティングに入ったシッターが捕まえて口をあけて薬を…となると、やっぱり怖がられてしまって、なかなかうまく飲んでもらえません…
昔、うちにいた子の投薬のときに、好きな食べ物やおやつに混ぜてみたり、蜂蜜に混ぜて上あごに塗るといいと聞いて試してみたりしたものの、結局、失敗。
口から泡を出しながら、不機嫌に逃げて行ってしまったり。
猫は苦味を感じると泡を吹いて苦味を口から出そうとするのです…^^;
口に苦味が出るより先に飲み込んでもらえればと、スプーンに薬を乗せて少しだけお水を入れてのどの方に流れるように飲ませてみたり…
未だに試行錯誤はしていますが、現状、一番成功率が高いのは小さく切ったオブラートで薬をしっかり包んでから、フードや好きなおやつに混ぜてあげる、もしくは、スプーンに乗せて少しのお水と一緒に口に入れてあげる。
オブラートに包むことで、苦味を感じないため、飲んでくれるようです。
運悪く噛んでしまったり、飲み込む前に唾液や水でオブラートが溶けてしまった場合は、やはり残してしまったり吐き出してしまったりもしますが、嫌がる猫さんを押さえ込んでの投薬は強いストレスになると思うので、飼い主様と相談しながら、できるだけ、無理のない状態でお薬を飲んでもらおうと、模索を続けています。
液体の薬については、犬も猫もシリンジ(注入器)を口の横から差し込んで飲んでもらいます。
シリンジならのどに近い口の奥のほうに薬を入れられるので、太めのシリンジに投薬補助用のペーストやゼリーに
粉薬や砕いた錠剤を混ぜて入れてあげるのもアリかもですね。


お薬ではありませんが、水分をあまり取ってくれない猫さんの水分補給にお水にCIAOちゅーるを入れるとたくさん飲んでくれるのでと、ちゅーる水をつくってあげていらっしゃるお客様もいらっしゃいました。
みなさん、「うちの子」のためにいろいろ工夫されているのは私も勉強になりますし、参考にもなりますし、飼い主様が「うちの子」を大事にされているのがわかることが、なによりも嬉しく思うのです(^^♪♪
2018-06-08 17:22:00
【飼う前によく考えましょう】
先日、こんなことがありました。
我が家で飼っているデグーのジロが、怪我をしました。
犬や猫なら状況を見て、どう対処するか、この程度なら病院に連れて行かないで様子を見て大丈夫そうとか、舐めるようならエリザベスカラーをつけるとか、ある程度の判断はできるのですが、デグーについてはどうしたらいいかわからず、動物病院に相談させていただきました。
デグーと暮らすのは初めてなので、迎えるときに必要なものを揃えたり、必要な環境を整えたりするためにデグーという生き物について知識を入れましたが、それでもやはりまだまだ知識や理解が足りていないこともあります。
生き物と暮らすためには、その子のことを知ることが必要で、良い関係性を作るためにも大切だと思います。
ペットとして飼われる動物たちは、習性や寿命、生活環境や必要な世話が大きく異なります。一般的なペットである犬や猫でも、その本能や習性を知らないで飼っている人は少なくありません。本などで調べたり、ペットショップで聞いてみるなどして、信頼できる情報を集めましょう。
同じ種類や品種のペットを飼っている人に話を聞いたり、実際に世話をさせてもらうこともよい気づきがあるかと思います。
また、生き物ですから当然個々の性格の違いもあります。購入したりもらってくる前のオーナーに、その個体の個性について聞いてみたり、親や兄弟を見せてもらうことも、その子のことを知る手がかりとなるかと思います。
広告や書籍の中には、「飼いやすい」「おとなしい」「利口」などいいことばかり書いてあるものがありますが、どんなペットにも長所と短所はありますし、飼う方のライフスタイルによって長所が短所になったりその逆もあります。その習性やその本能、生態、必要な施設・設備などをきちんと調べ、知ることで、ペットとよりよく暮らすことができるようになると思うのです。
また、怪我や病気のときに診てもらうかかりつけの病院を決めておくことや、引越しや入院などでお世話ができなくなったり飼い続けることができなくなった場合に譲り受けてくれる人やお世話をしてくれる人など見当をつけて置くといざというときに安心かと思います。
参考文献:環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 発行「飼う前に考えて!」
人とうまく暮らすために必要なしつけなどもできれば早いうちに教えてあげれば覚えも比較的スムースですが、しつけ方もその動物の特性を知らなければ上手に覚えてもらうことは難しいので、なにしろ、その子がどういう子なのかをわかってあげることが一番かと思います。
わかってくれる飼い主さんと一緒にいる動物も、きっと幸せだと思うのです。
せっかく縁あって一緒に暮らすのだから、楽しい時間、幸せな時間をいっぱい過ごしたいですよね。

2018-06-03 22:54:00
【ドッグフードの正しい保存方法】

愛犬家の皆様どんな方法でフードの管理をされておられますか?
先日、お客様からワンちゃんの下痢が止まらず心配なので様子を見にきてもらえませんか?とご相談を受けました。
下痢が始まってから3日目のことです。
詳しく状況をお聞きしましたが、お散歩中の拾い食いは無く、フードも普段と同じ物を食べさせているとのことでした。
様子を見に行くと、普段は外でしかうんちをしないワンちゃんですが、我慢が出来ず、お部屋でうんちをしてしまっていました。うんちの状態は完全に水便です・・・。
お散歩に行くと、やはりお腹の調子が悪く、頻繁に少量の水便を出す状態でした。
心配な状況ですので、飼い主様に病院の診察をお勧めしたところ、どうしても仕事が休めないとの事したので、翌日、私がワンちゃんを連れて、病院の診察を受けることになりました。
以下、滋賀県大津市の動物病院の先生のお話になります。
出来ればうんちを持ってきてくださいとのことでしたので、
お散歩中に出た水便を持参し、検査してもらいました。
結果、通常から腸内にいる悪玉菌の数が増殖して腸炎を起しているとのことでしたが、ウィルス感染はしておらず、ほっと一安心です。
原因の可能性として、
1.ストレスや寒暖差の激しい時期に身体がついていけていない。
2.お散歩中の拾い食い。
3.ドッグフードの管理方法の甘さからくるフードの変質。
などがあります。
多いのは、ドッグフードの変質、油脂分の酸化だそうです。
飼い主様の中にはドライフードだから日持ちもするし大丈夫と思っておられる方も多いと思いますが、基本的には封を切ってから1ヶ月以内、夏場など暑い時期は2~3週間以内に使い切るのがよいそうです。
その理由としては、ドッグフードには動物性、植物性の油脂が含まれており、空気に触れた瞬間から酸化が始まり、過酸化脂質に変質するからだそうです。
過酸化脂質を摂取し続けると健康被害(動脈硬化、ガン、アレルギー疾患)などを起す原因になるといわれております。
その他にも、高温多湿や光(直射日光、照明)による酸化もあるとの事です。
見落としがちですが、ドッグフードをよくよく確認するとカビが繁殖していることもありますよ、とのことでした。
では、どのようにフードの管理をすればよいのでしょうか?
小袋のフードを購入して、常に新しいフードを食べてもらうのが理想ではありますが、特にプレミアムフードは大袋に比べると割高になってしまいます。
そこで管理方法として、
1.袋を密閉容器に入れる。
2.密閉容器は冷暗所へ置いておく。
3.1カ月以内に使い切る。
それでも1ヶ月以内に使い切るのが難しいときは、毎食分をジップロックなどの小袋に入れ密閉保管をする。
冷蔵庫に保管する。
という方法が望ましいそうです。
この冷蔵庫に保管するときの注意点は、1食分ごとの使いきりであれば問題ありませんが、大袋をそのまま入れるのはお勧めしません、との事です。
理由として、冷蔵庫と室内の温度差により、フードの袋に結露がつきやすく、水分量が増えてカビが繁殖してしまいやすいからだそうです。

皆様の大切なワンちゃんによりよい食事をしてもらい、いつまでも元気に過ごしてもらうための参考になりましたら幸いです。
2018-06-02 23:09:00
【ゆっくり仲良くなろう】
気温が上がってきて、戸外にもたくさんの草花が咲いています。
お散歩わんこの通り道にも紫陽花が綺麗に色づいていて、
梅雨の季節を彩ってくれています。

さて、このルートをお散歩しているトイプーのクーちゃん。
怖がりさんで、最初のうちはなかなか一緒に歩いてくれませんでした。
クーちゃん、お散歩いこーって誘っても、
↓こーんな顔で「え~?この人と~?む~…」って…

でも、何度も何度もお散歩に行くうちに慣れてきてくれて
今ではお迎えに行くと、キライなはずの雨の日でも
早くいこーーー!!! と引っ張りながら
お気に入りの川の土手までダッシュ、
ご機嫌にハイテンションでお散歩を楽しみ、
↓こーんな風に笑ってくれるようになりました。

最初からフレンドリーな子はお散歩もはじめから楽しんでくれて、
喜んでもらえて嬉しいです。
でも、回を重ねて顔を合わせるうちに、こんな風に距離が縮まる子も、
また違った嬉しさをくれる、素敵な子なんです。
クーちゃん、これからも一緒に季節ごとの空気を楽しもうね。
2018-05-31 21:14:00
【ペットとの暮らしと掃除】
動物と暮らしていると、
人間だけで暮らしているときには出ないゴミが出たり、
特に換毛期などは抜け毛でお部屋がすごいことになったりします。
掃除道具は皆さんいろいろと考えていらっしゃって
勉強になることもたくさんあります。
ゴミの処分は各自治体によって違いますし、
トイレシートや猫砂などは製品ごとに処理の方法が違うので
確認して捨てます。
気温が上がるこれからの時期、おしっこやうんちは臭いが気になります。
臭いの強い子のうんちなどはゴミの収集日まで保管しておくにも
工夫をしないとかなり臭い漏れがしたりします。
そういうときは、臭いを防ぐビニール袋を使うとかなり臭いを封じ込めることができます。
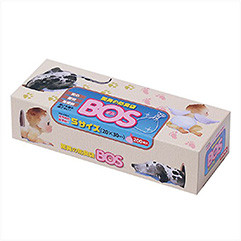

ちなみに、犬猫のうんちをトイレに流すケースもよくあるのですが、
犬猫のうんちは詰まりやすいので、一度に大量に流したり、
水勢の弱いトイレなどでは流さないでゴミで捨てるなど、気をつけてください。
実際に詰まって大変なことになることもあります。
さて、猫トイレの砂の飛び散りは、私はたいてい小箒で集めます。
100均にあるプラスチック製のちりとりがセットになっているものは
洗えるし置き場所も取らないので使いやすいです。

コードレスタイプの掃除機で吸い取る方も結構いらっしゃいます。
この場合、ある程度吸引力が強くないと砂を吸い上げてくれないのですが、
ダイソンの掃除機は置き場所も取らず、吸引力も強いので、
使われているお宅が多いように思います。

個人的にはマキタのコードレス掃除機が好きなのですが、

こちらはダイソンよりは吸引力が劣るので、
重さのある砂だと吸い上げられなかったりしますね。
なので、仕上げは結局、小箒かな。
掃除機は楽で手軽でよいのですが、
風で毛埃が舞い上がってしまうのが難点です。
毛埃が多いときの床の掃除はフローリングワイパーがお奨めです。

ワイパーを床にスーッと滑らすだけで
楽にすっきり毛が取れますよ♪
ウエットシートよりもドライシートの方が毛はよく取れます。
音を怖がるペットさんを驚かすこともありません。
100均にもありますし。
フローリングワイパーで絡み取れなかった小さなゴミは、
最後に小箒で集めるか、ハンディ掃除機で吸い上げれば完了です。
粘着式クリーナー(コロコロ)も便利ですね。

これも100均のものでも十分使えますね。
ペットベッドやキャットタワーなども、
小さめのコロコロなら掃除しやすいです。
小鳥の羽毛なども舞い上がりやすいのですが、これなら大丈夫。
カーペットももちろんコロコロしますが、
カーペットなどの布物は結構毛が絡み付いていて
コロコロだけではすっきりしないことがあります。
そんなときに登場するのがラバーのペットブラッシングブラシです。

ゴム素材のブラシは毛埃をカーペットや布から剥がして浮かせてくれます。
浮いた毛を集めて、仕上げはコロコロで。これでかなりすっきりします♪
ゴム手袋でカーペットを撫でても埃は取れるのですが、
毛足の長めのカーペットなどはブラシ状のものの方が使いやすいです。
日常生活の中では、
なかなかお掃除に時間をかける余裕もなかったりするものですが
できるだけ楽にすっきりできれば気持ちいいですよね(^^♪